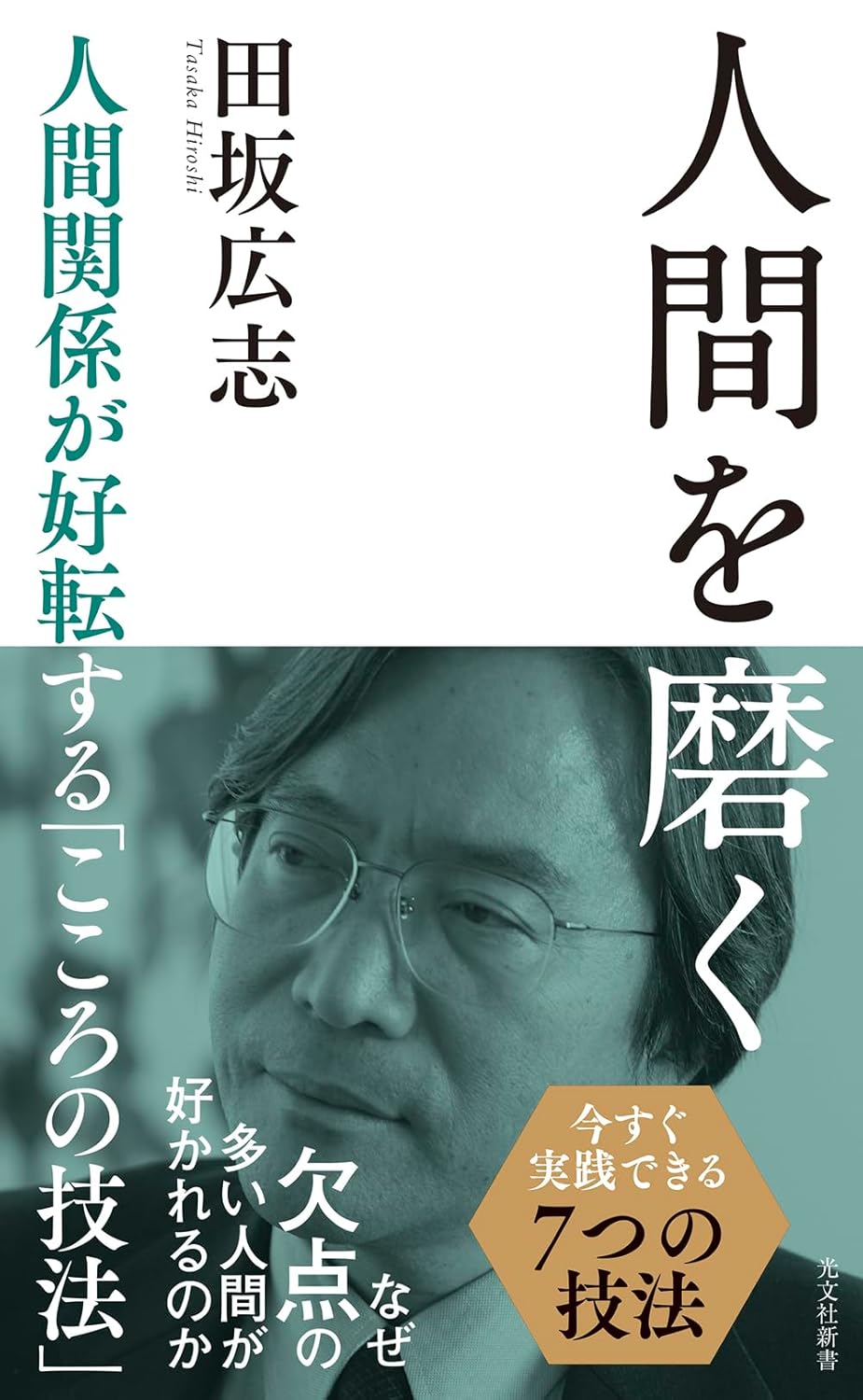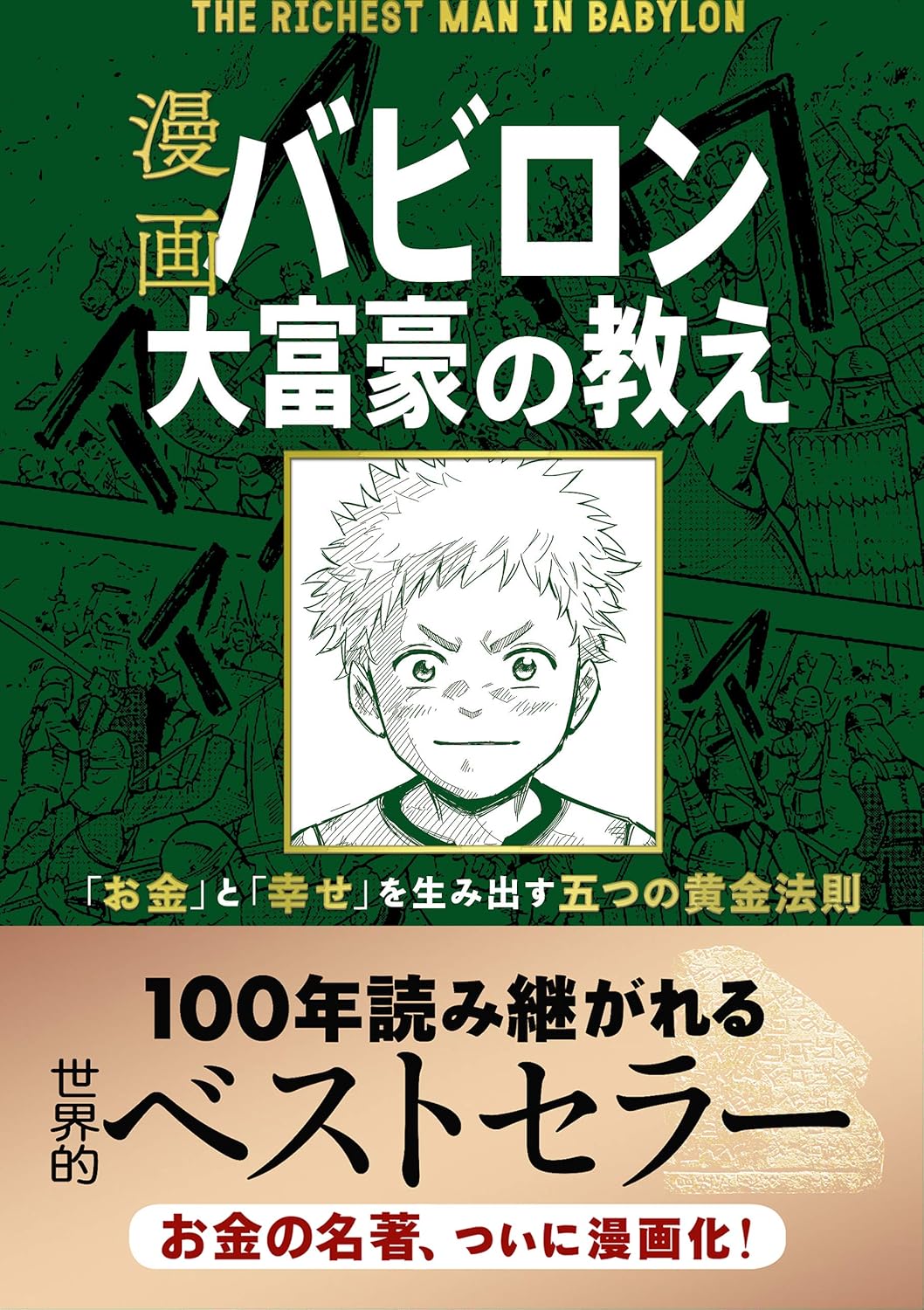現代と真逆の消費を促した3つの要因とは
1980年代後半から1990年代初頭のバブル期、若者は給与水準に大きな差がなかったにもかかわらず、無理をしてクルマを購入していた。なぜ、あれほど背伸びして手に入れようとしたのか。
バブル期は日本で1986(昭和61)年12月から1991(平成3)年2月まで続いた。土地や株式などの資産価格が実体経済を超えて急騰した好景気である。異常な資産高騰と、その後の急激な下落をともなう現象から「バブル景気」と呼ばれた。
背景にはいくつかの要因があった。まず、1985年のプラザ合意による円高で輸出産業が打撃を受けたことだ。
次に、日本銀行は政策金利を2.5%まで引き下げ、低金利環境が長く続いた。さらに公共投資の拡大や税制改革によって可処分所得が増えたことも大きい。これらが低金利や資産効果と相まって、企業や個人は株式や不動産に資金を集中させた。特に「土地は必ず値上がりする」という信念が、不動産投資を加速させた。
経済や社会への影響も大きかった。1989年末の日経平均株価は3万8957円に達し、東京圏の地価は数年間で倍増した。キャピタルゲインを得た企業や家計は消費や投資を活発化させ、銀行は土地や不動産を担保に巨額融資を行った。
しかし、1990年代初頭、日本銀行が急激な金融引き締めを行うと株価と地価は急落した。不良債権が拡大し、経済は長期停滞期に入った。「失われた10年」と呼ばれる時代で、企業や家計の金融負債も増加した。
総じて、バブル景気は実体経済を超えた資産価格の過剰上昇と、それにともなう投機的行動によって作り出された異常景気である。政策の失敗と心理的過熱が重なり、崩壊後には長期的な経済停滞をもたらした。
バブル期の新卒初任給は15万~18万円程度で、現在と大差はなかった。しかし高級車や外車は300万~500万円と高額で、給与だけで購入できるものではなかった。多くの若者は親の援助やローンに頼らざるを得ず、家族や金融機関の支えが前提となる購買行動が一般化していた。
当時、ディーラーや銀行は自動車ローンを積極的に提供した。頭金がほとんど不要な購入プランも一般化しており、将来の給与は増える、返済に問題はないという楽観的な心理が広がった。土地や株価の急騰により、社会全体が豊かさは永続すると信じる空気も影響した。この環境は、若者に実質以上の購買力を持てる錯覚を与え、ローンを利用して高額車を手に入れる行動を正当化した。
クルマはただの移動手段ではなく、社会的地位や自己表現の象徴でもあった。広告や雑誌はクルマを持つことを大人や成功、モテることと結びつけ、繰り返し強調した。特に若者にとって、デートやレジャーにクルマは必須であり、所有しないことは周囲から取り残されることを意味した。さらに、テレビや映画で描かれるライフスタイルもクルマ中心であり、流行や文化が購買欲を刺激した。
1980年代後半はブランド品や高級消費が日常化し、背伸びすること自体が評価された。職場や友人がクルマを買えば、自分も購入しなければ劣等感を覚えた。周囲に合わせる消費行動は、クルマ購入をさらに後押ししたのである。
バブル景気特有の過熱した消費文化は、同調圧力と結びつき、個人の判断より社会的評価が購買の動機となる現象を生んだ。
まさに錯覚と同調の消費心理といえる。
土地や株の価格が急騰し、社会全体が豊かさは拡大すると信じていたため、若者は給与以上の生活水準を当然視した。「今買わなければ損」という心理が消費を正当化し、現実を超えた購買行動を生んだのである。バブル期のクルマ購入は、
・金融環境
・文化的価値観
・社会的圧力
が複合的に作用した結果だったといえる。
では現代の若者が無理して買わない理由とはなにか?
バブル期の若者はクルマを持つことを当然と考えていたが、現代の若者はむしろ「クルマは必須ではない」と考える傾向が強い。その背景には、当時とは正反対の社会構造がある。
現代は非正規雇用の拡大や昇給の鈍化で、将来の収入増が見込みにくい。ローンを組んで背伸びする心理的余裕は薄れ、生活の安定を優先する意識が強い。無理に高額なクルマを購入するリスクを避ける傾向が顕著である。
加えて住宅費や教育費、医療費など生活費の負担も増し、自由に使える可処分所得が減少していることも心理的な抑制要因になっている。
都市部では公共交通が発達し、カーシェアやレンタカーも普及した。「必要なときに借りればよい」という選択肢が現実的になり、クルマの必須性は大きく低下した。
地方でも維持費や税金、駐車場費用が重くのしかかり、マイカーを所有することは必須ではなくなりつつある。都市計画の変化でコンパクトシティや駅近居住が増え、クルマなしでも生活が成り立つ環境が整いつつある。
SNS時代の若者はクルマよりもファッションやガジェット、旅行体験など「共有可能な経験」に価値を置く。かつてのようにクルマがモテや成功の象徴ではなく、ステータスとしての力は低下している。情報が瞬時に拡散する社会では、消費の価値は「見せること」より「体験の質」にシフトしている点も影響する。
さらに、気候変動や脱炭素が意識されるなかで、燃費の悪いクルマを所有することに後ろめたさがともなう。若者は所有より利用、浪費より合理性を重視し、消費行動に環境意識や社会的評価が反映される傾向が強い。こうした背景から、クルマ離れは単なる個人の趣向ではなく、社会全体の構造的変化として理解できる。
KINTO(愛知県名古屋市)が実施した調査によると、普通自動車免許を持つ東京都内在住のZ世代(18歳~25歳)309人と地方在住のZ世代300人を対象に、2025年版「Z世代のクルマに対する意識比較調査」を行った。なお、本調査は2022年からの定点調査である。
調査では、東京都内のZ世代の72.8%が「若者のクルマ離れ」を実感しており、昨年より21.5ポイント増加した。83.7%が「クルマのサブスク」を検討しており、都内では92.0%と需要の高まりが顕著だった。また賃上げを受け、都内の8割、地方の約7割が、収入が増えれば「消費を増やす」と回答している。
あの時代、若者は背伸びをしてでもクルマを手に入れた。低金利の追い風や金融のゆるさ、周囲からの「持っていて当然」という圧力、そして何より未来への楽観がそれを後押しした。クルマは青春と自由の象徴だった。
現代の若者の事情はまったく異なる。雇用や収入の不安定さ、公共交通やカーシェアの便利さ、価値観の変化が影響し、クルマに多額を投じる心理的余裕は失われた。給与水準は同じでも、社会や制度、文化が変われば、消費行動はまったく逆に動くことがわかる。
しかし、あの時代のクルマには、現代では味わえないワクワクがあった。週末に仲間とドライブに出かけ、カーステレオを大音量で鳴らしながら街を走る。色やカスタム、ささいな瞬間までもが青春の1ページに刻まれているだろう。
この記事を読む読者には、ぜひ当時の思い出をコメントで語ってほしい。
「あのクルマでこんなことをした」
「あの頃はこんなに自由だった」
といった体験だ。現代のクルマとの違いも含めて共有すれば、バブル期の青春が再び鮮やかに蘇るだろう!