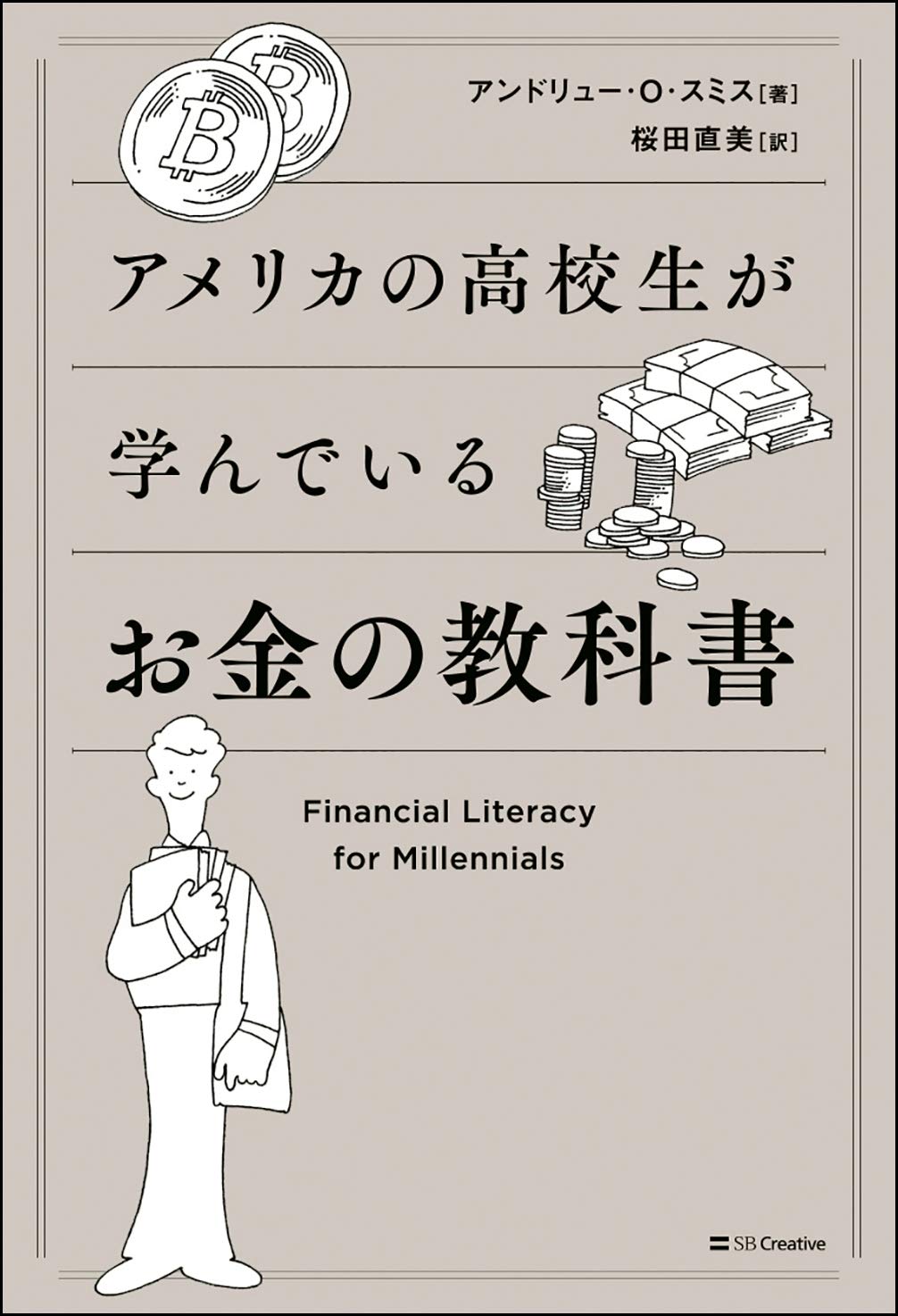金融とエンタメ連携
日本で映画等映像作品を作る場合、テレビ局や広告代理店、出版社など直接の制作関係者が資金を出し合う製作委員会方式が一般的。
規制などの面から金融機関など外部の出資が難しく、大型作品の制作では資金面で国際競争に劣後しやすい環境になっていました。
一方、米ハリウッドでは金融機関や投資家など直接の制作関係者以外から制作資金を呼び込む手法が存在します。
映画ごとに特別目的会社(SPC)をつくり、SPCの株式を販売し投資を募り制作資金を調達する訳です。
国内でもようやく映画ファンドへの関心が高まり始めた様子。
東映出身者らが設立したK2ピクチャーズは映画ファンドを立ち上げ、100億円規模の資金調達を目指すという。
同社は3日、任天堂創業家の資産運用会社「ヤマウチ・ナンバーテン・ファミリー・オフィス(YFO)」と資本提携を結び、約11%の出資を受けたと発表した。
三菱UFJフィナンシャル・グループも25年6月3日、映画を制作するための新たなファンドを立ち上げたと発表しました。
講談社と漫画「キングダム」の実写映画の制作会社と提携し、新たな資金調達の仕組みをつくり、他の投資家の資金を含めて三菱UFJ信託銀行がファンドを組成・運用する。
金融機関とエンタメ企業が組み、1つの大型作品を対象とした資金調達手法としては国内初の事例とみられる。
三菱UFJは2021年の銀行法改正で銀行の手掛ける業務範囲規制が緩和されたことを受け、新規事業の開発を進めている。
成長が見込まれるエンタメ産業との取り組みを通じてビジネスを育てる狙いがある。
今回は資金の出し手と制作の担い手を分離することで金融機関や投資家が安心して資金を出しやすくした。
一方、作品の未完成リスクや収入が計画より下回るリスクもある。ファンドや合同会社の維持コストも相応にかかるため、三菱UFJは資金供給の選択肢の一つとして取り組む考えだ。
参照:日本経済新聞
金融機関がやっと重い腰を上げたという印象。
近年、Netflix、amazon prime、ディズニープラスといった、サブスク配信サービスが盛況なこともあり、アメリカで上映が決まった大型映画が、当たり前に日本で観られるとは限らなくなった。
作品を観る手段が、映画館というシステムに限定されなくなったからだ。
昔は新作は全て映画館で観て、遅れてビデオレンタル、更にだいぶ遅れて日曜洋画劇場にて淀川さんに紹介されるという流れだったものだ。
いつかオンデマンドが主流になって、レンタルビデオ店は無くなると聞いていたが、確かにそうなった。ひとつ大きな時代の変化と言って良いのではないだろうか。
そして、そんなサブスクの国内トップの規模を誇っているのは、Netflix、amazon prime、ディズニープラスと、見事に外資(アメリカ)が席巻している状態である。
そして近年、外国資本のお陰で、兼ねてから実力を認められつつあった日本の制作会社が、実際に世界に通用すると示している現実がある。
「将軍」や「ガンニバル」といった、ディズニーから豊富な資金を得て世に送りされた作品は世界的な評価を受けており、今までの日本映画に足りなかったものは唯一、資金だけであったと証明する形になってしまった。
そこに来て、今回の記事という流れになっている。
外資の力で、日本の映画制作会社に投資する価値が有ると証明できた為、国内大手銀行がファンドに乗り出したわけだが、まぁ…何と言うか…、石橋を叩いて渡るというか、二番煎じでリスク無し。
晴れの日に傘を貸し、雨の日に取り上げる、とは、国内銀行の融資スタンスを揶揄する言葉である。
今回は、ファンドであるから同じではないけれども、外資の資本でテストをしてから国内資本で初の試みとか言われても、どうにも日本から新たなものが生まれない理由を突き付けられているように感じてしまう。
かつて韓国が、国を揚げてアジアのハリウッド「韓流」に挑んだように、リスクを取り覚悟を決めて世界に挑戦する気概。
そういったスピリットが、日本には失われていると感じてしまう。
危なげなく、既成路線で小銭を稼ぐことを覚えた結果、この数十年は日本全体で資産は目減りし続けている。
やり方よりも、在り方。
その姿勢に課題があるのではないだろうか。
今、日本人に求められているもの。
それはまさに、失われてしまった、かつてのサムライスピリッツなのかも知れないと感じる。