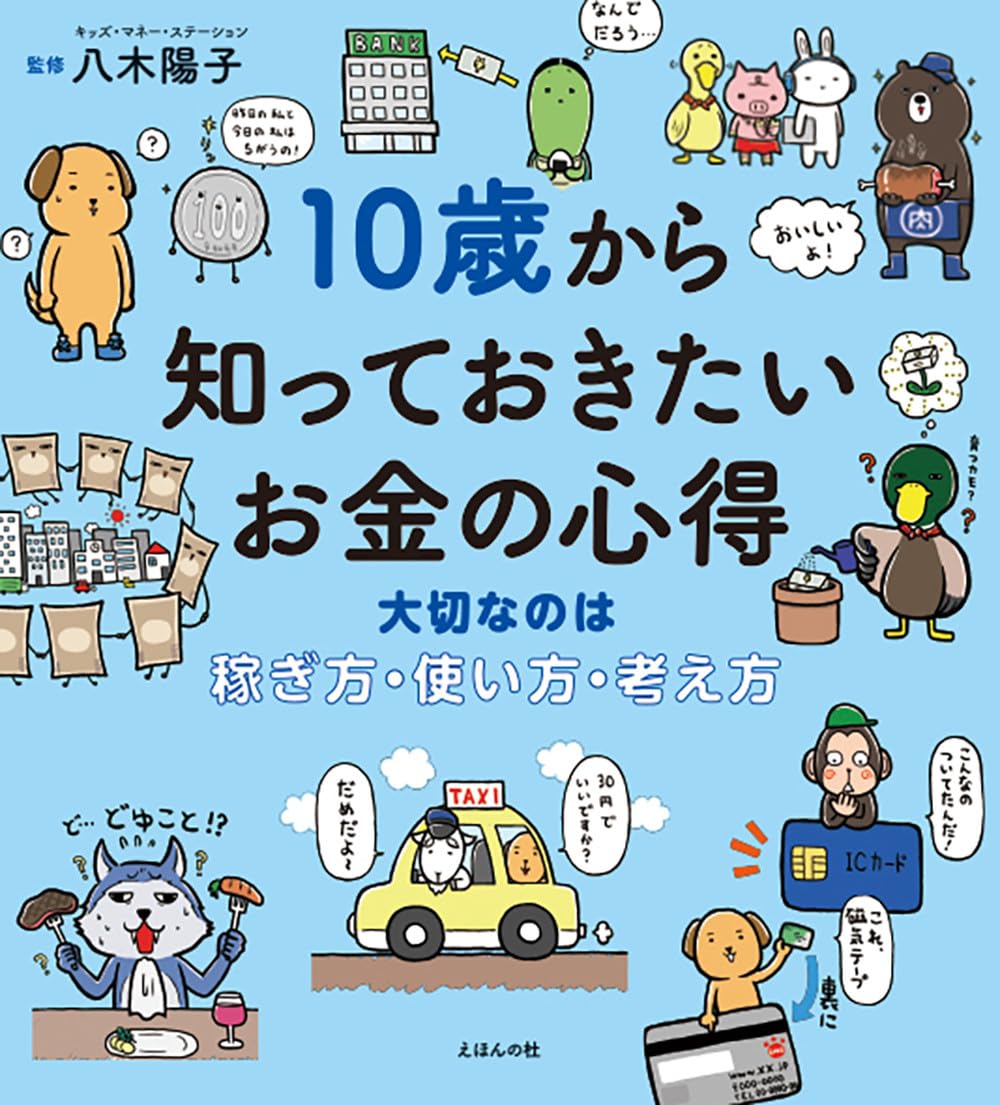生命保険会社が保有する超長期債に減損のリスクが迫っている。
生命保険会社は契約期間の長い保険商品を販売しており、抱える負債が長期に及ぶ。その間の金利リスクを抑えるため、資産とし償還期間が超長期の債券を購入する。
主要13社・グループの国債などの国内債券の含み損は3月末時点で16兆8500億円と前年3月末の約4倍に膨らんだ。
日本生命保険など大手4社は約4倍、富国生命保険や朝日生命など中堅9社は約5倍となった。
40年物など国債の減損リスクが高まっている。現行の会計基準では保有資産の時価が取得価格の50%を下回って回復の見込みがない場合、減損処理をしなければならない。
金利上昇で保有債券の価格が急落し、一部の債券の時価が簿価の50%を下回るケースが出て来る可能性がある。
保有債券を減損処理する際には、評価差額を有価証券評価損として計上する必要がある。年度末までに時価が回復しなければ、剰余金などが減る為、保険の契約者に支払う配当を圧迫する恐れもある。
影響が大きいのが中堅生保だ。朝日生命や24年度中に一部債権の時価が簿価の50%を下回った。当該債権を売却せずに継続保有する事を宣言し、実際の減損処理を回避した。
債券は満期保有すれば元本が返還される為、長期保有を宣言すれば回復の見込みがあると判断される場合もある。別の中堅生保でも同じような事例があった。
含み損を抱える債権を新たな債券の購入で入れ替える場合、損失を確定しなければならない。大手は株式や外国債券など他資産の含み益を多く抱える。損が出ても埋め合わせる事が可能だ。しかし中堅は債券の比率が悪く、十分に入れ替えが勧められない恐れがある。
日本生命の国内債の含み損率はマイナス11.7%で有価証券の全体の含み損益は73619億円。
第一生命はマイナス11.1%、含み損益は4443億円
明治安田生命はマイナス7.7%、含み損益は34278億円。
住友生命はマイナス10.5%、含み損益はマイナス1401億円。
中堅の富国生命はマイナス5.1%、含み損益は6856億円。
その他中堅生保の含み損率は二桁、含み損額は大同生命マイナス3277億円、太陽生命178億円、朝日生命108億円、ソニー生命は22384億円と、大きく転落した。
運用資産に占める国債比率が高い中堅財務に金利上昇はより大きく響く。
金利上昇で保険は利回りの高い他の金融商品に顧客が移るリスクもある。解約が増えた場合、保有債券を売却する必要が出て来るためだ。
大量の解約が想定される中では、満期保有の宣言が認められずに減損処理を迫られる可能性がある。金利の先高観が強まる中、生保の資産管理は難易度を増している。
【ツケ】
2000年頃から20年近くに渡り、日本経済は永遠にデフレであるかのように、赤字国債を乱発し続けて来たツケが今、日本の大手金融機関を襲っている。
日本の赤字国債を、大口で引き受け続けて来た歴史があるからだ。
そうして来た理由は、【金利が下がる(デフレ)限り、債権価格は上昇する】からである。
今までは政府の赤字国債を、日本の大手金融機関が買えば買うほど、保有しておけば勝手に毎年、帳簿上の利益は上がっていた為、それで良かったが。
ご存知の通り現在、【金利が上がる(インフレ)限り、債権価格は下降する】という真逆のトレンドに入ってしまったわけであるから、この十数年間、国債を買い溜めして来た大手金融機関の莫大な保有国債は、年々、帳簿上に損を刻み続けるわけである。
さぁ、大変だ…。決して対岸の火事ではない。
そしてこれは、またも国民に対して結果的にツケが回ってくる話になって行く。
物価が上がる(インフレ)のに、ある時から預金金利が上げられなくなるのである。
理屈はこうだ。
政府は、不景気なデフレ時代(失われた20年)を支える為、赤字国債を散々購入した金融機関をほってはおけない。
そこで、政策金利(日銀が銀行に貸す金利)を上げられなくなる。(上げれば上げるほど、保有国債の含み損が大きくなるからですね)
そうすると金融機関は助かるが、国民は相変わらず物価が上がり続けているのに、銀行金利は上がらないわ、保険会社の商品の利回りも上がらないわで、民には何も恩恵が降ってこないと、こうなるわけである。
国民に今必要なのは、自営&自衛策なのかも知れない。せめて、自分と近しい人達を守る術くらい、手に入れたいものである。