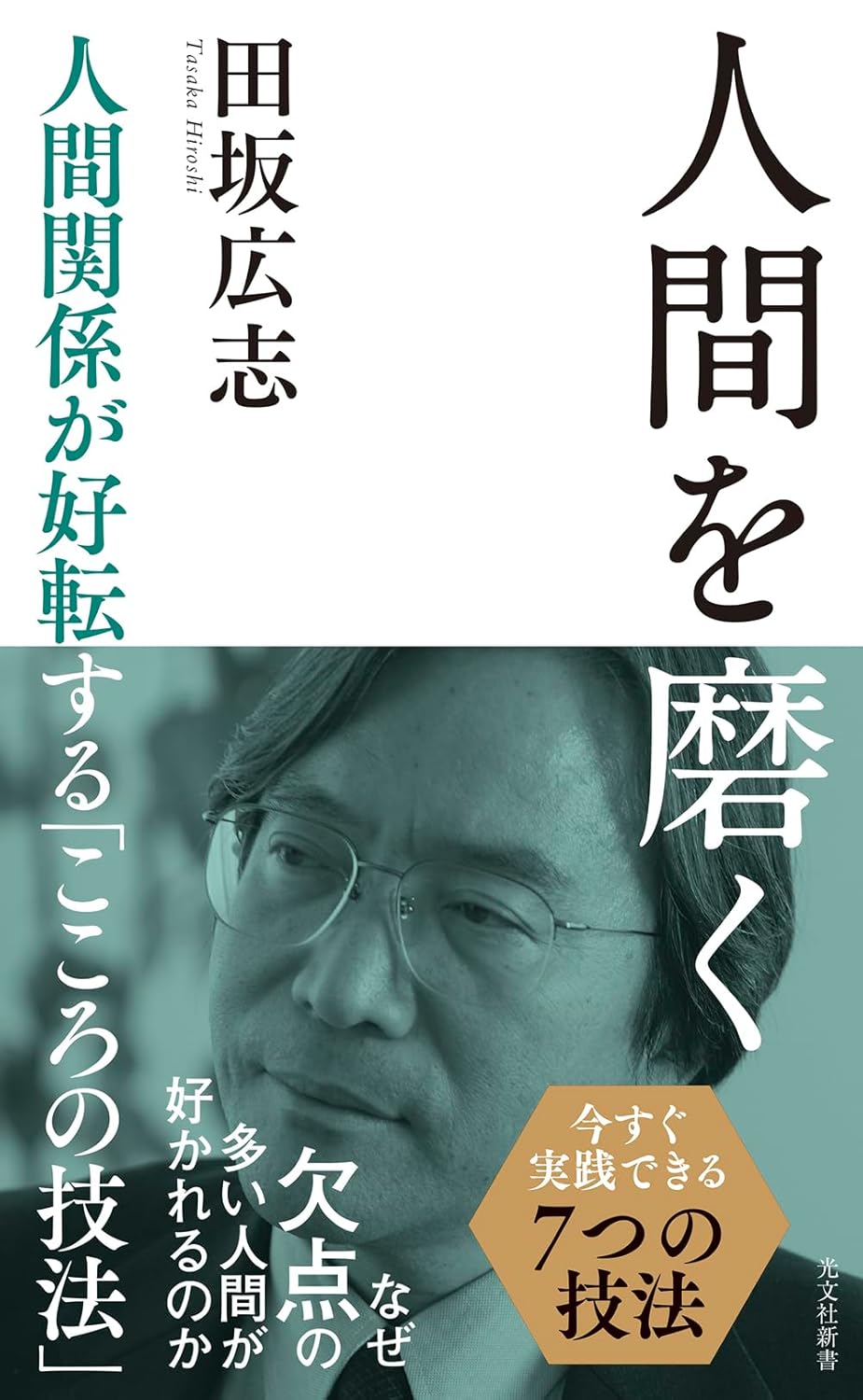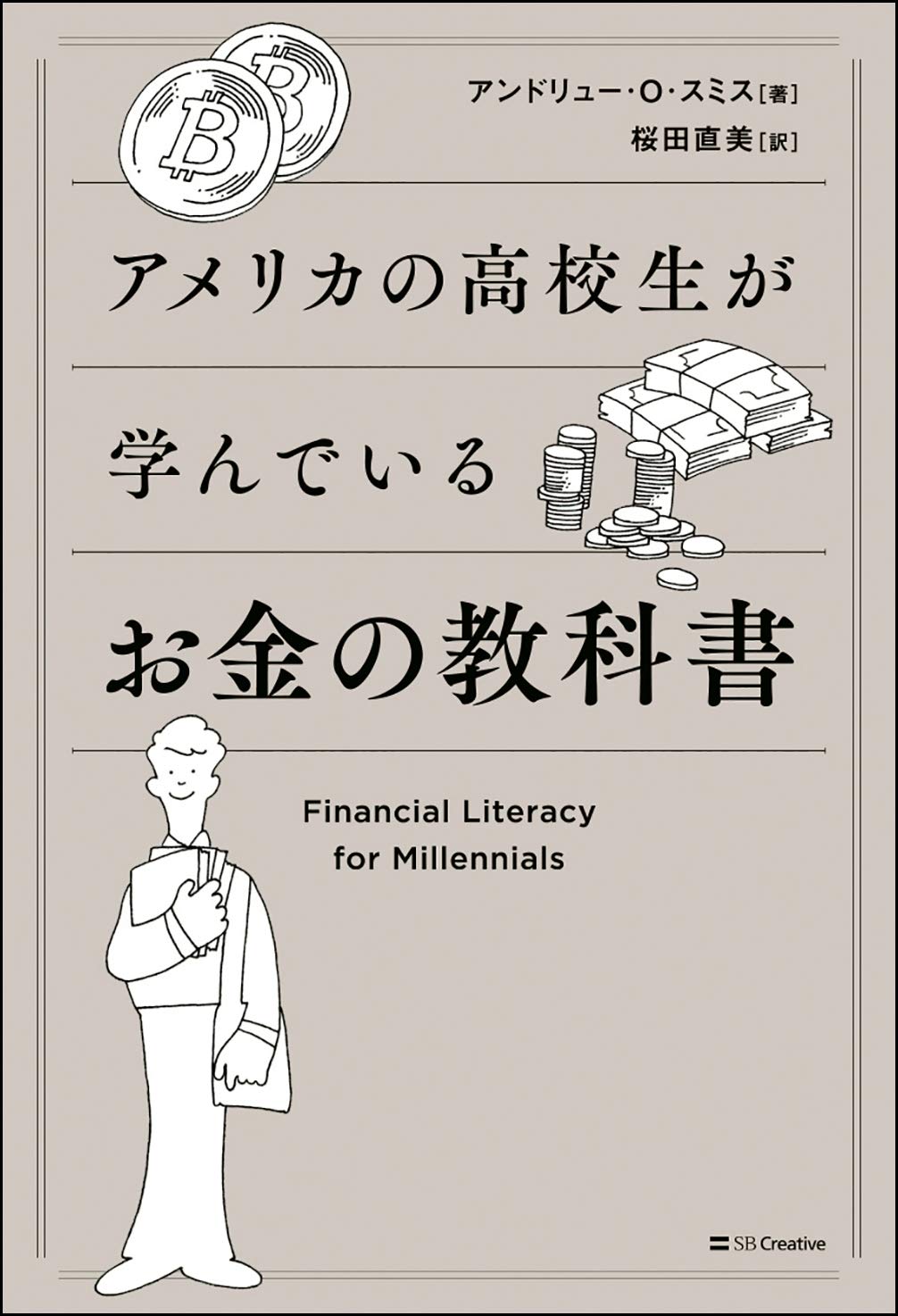日銀は20日、4月30日〜5月1日に開いた金融政策決定会合の議事要旨を公表した。9人の政策委員は米国の関税政策による経済などの下振れ懸念を共有したものの、複数の委員は「これまで同様、政策金利を引き上げていくのが適当」との認識を示した。
委員は「経済・物価の見通しが実現していくとすれば、経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことが適当」との見方で一致した。
このうち1人は「賃金・物価が上がりにくい頃の状況に戻るリスクは小さい」と指摘し、「2%に向けて上昇してきた(一時的な変動要因を除いた)基調的な物価上昇率が下方に屈折する可能性は小さい」とも述べた。
日銀は同会合で「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」も公表した。多くの委員が「今後の各国の通商政策の動きや企業・家計の対応次第では経済・物価の見通しが大きく変化する可能性がある」という考え方を共有した。ある委員は「サプライチェーンの混乱が長引けば、基調的な物価上昇率を押し下げる要因として作用する可能性がある」と述べた。
国債買い入れ減額の中間評価についても議論した。ある委員は「日銀が一時的な需給バランスの変化に都度対応すると市場の機能を再び損なってしまう」と指摘した。
参照:日本経済新聞
バブル崩壊後、十数年から、ほんの少し前まで日本国内の全銀行金利は、定期預金0.01%/年であった。
それが現在は、0.3%/年であることを考えると、あっという間に30倍に上がったということだ。
先のUSスチール買収劇に見て取れるように、日本はようやく本当に進み出した。
それに伴い、金利が上がるのである。
現在、政策金利(日銀が傘下の銀行に貸す時の金利)が0.5%/年であるが、おそらく1%/年くらいまでは、あれよあれよという間に上がるであろう。
しかし気を付けて頂きたいのは、預金金利の利率でお金増えても、豊かになることは無いという事。景気が良くなり、家賃や物価が上がった分を補う形でしか、預金金利(政策金利と連動)は上がらないからである。
あくまで預金金利の数字を基準にして、それより有利な金利を提示してくれる商品を、自分で探さないといけないのだ。
預金金利より大幅に高い金利を提示された場合は、逆にリスクの高さも、しっかり把握する必要がある。
大手保険会社が預金より少し高い金利を提示し、その分リスクの低さを謳っている商品(N生命:ちょこ積み、S生命:茶巾)が人気のようだが、本当にそれで描いた未来に続いているのか考えなくてはならないだろう。
日本人が本当に投資に向き合わねばならない時代は、正にこれからやってくる。